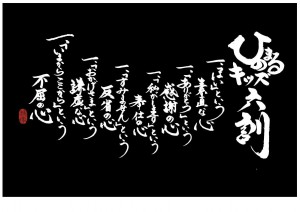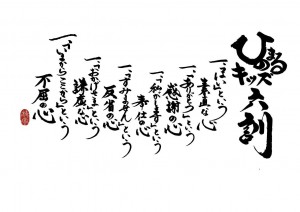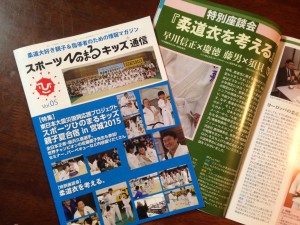先週の土日は、日本武道館に
高校選手権の取材に行っていました。
男子は、昨年の高校三冠メンバーを3人残し、
大本命と言われた国士舘高校が決勝でまさかの敗退。
日体荏原高校が初優勝を果たしたのでした。
この日の日体荏原は、一人ひとりが
本当によく活躍していました。
2回戦の静岡学園戦では先鋒の百々雄弥君が4人抜き、
続く3回戦の津幡戦と、4回戦の天理戦では
次鋒・長井晃志君が2試合連続3人抜き。
準決勝の木更津総合戦では、先鋒の大吉賢君が4人抜きと、
試合毎に入れ替わりのヒーローが誕生。
準決勝の木更津総合戦に関して言えば、
73㎏の大吉君が、145kgの先鋒、110kgの次鋒、128㎏の副将に
いずれも裏投げで一本勝ちという、驚愕・圧巻の戦いぶりでした。
勢いに乗ったら手がつけられないというのは、
まさに、こんな状況を言うのでしょう。
決勝の“難攻不落”と思われた国士舘戦でも、
その勢いは止まりません。
この試合では、副将のハンガル・オドバートル君が
国士舘のエース格の2人を抜く大活躍を見せたのでした。
この日体荏原の勢いは、
前日の個人戦(81㎏級優勝)で疲労の残る
大将の藤原崇太郎君を、
できるだけ楽させてやろうと
チーム全員が一丸となったことで
生まれたのではないかと思います。
そして、その仲間の熱い気持ちに応えたのが、
キャプテンであり、大黒柱の藤原君でした。
高校選手権2連覇、インターハイ優勝の
藤原君ですが、体重は81㎏級。
決勝の相手、国士舘の飯田健太郎君は、
100kg級のインターハイチャンピオンで、
超高校級と言われる最強豪選手。
過去の対戦では、2回続けて負けていました。
でも、仲間が頑張り、決勝まで1試合もせずに
“温存”されていた藤原君は、
「ここで俺が勝たなきゃ、なんのためのキャプテンだ!」と奮起。
難攻不落の飯田君から、執念の背負い投げで「有効」を奪い、
勝利したのでした。
新しい歴史の1ページは、まさに“仲間との絆”で
生まれたと言っていいと思います。
国士舘の無念と日体荏原の歓喜。
勝負の難しさと面白さ、
あきらめない気持ちの大切さ、仲間との絆、
いろいろなものを感じた今年の高校選手権でした。
柔道ライター 兼 ひのまるキッズ事務局 林 毅