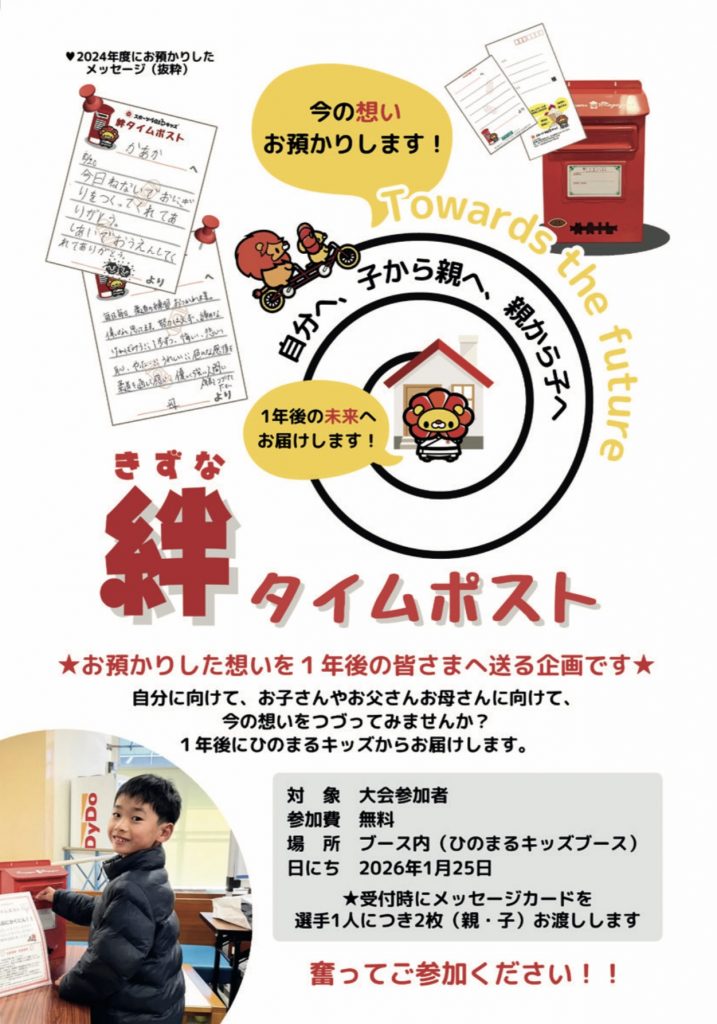こんにちは、中村です。
「ウタマロPresents 第17回スポーツひのまるキッズ九州小学生柔道大会」を、 1月25日(日)に北九州市立総合体育館にて開催いたしました。
過去最多となる約1,000組の親子にご参加いただき、会場は大きな熱気と笑顔に包まれました。

大会当日
開会式では、皆勤賞の15名の選手が表彰され、講師の角田夏実先生、髙山莉加先生より、オリジナルタオルが贈られました。
 角田先生と髙山先生からオリジナルタオルが贈られました
角田先生と髙山先生からオリジナルタオルが贈られました
皆勤賞の選手と講師6名での記念撮影も行い、会場からは温かい拍手が送られました。
 記念撮影
記念撮影
続いて、選手宣誓では柔誠会の荒木親子に立派な宣誓をしていただきました。
 荒木親子による選手宣誓
荒木親子による選手宣誓
開会式の最後には、柔道マガジン3月号掲載用の集合写真を撮影し、いよいよ九州大会がスタートしました。
 集合写真
集合写真
チャレンジマッチ
今回のチャレンジマッチには、12名の選手が参加しました。
講師の朝飛大先生による準備体操と礼法指導の後、試合に挑戦。
勝敗よりも「挑戦する気持ち」を大切にし、一人2試合を行いました。
初めて試合に出場する選手も多く、緊張しながらも最後まで全力で取り組む姿がとても印象的でした。
試合後には、朝飛先生から一人ひとりに「良かったところ」「頑張っていたところ」を伝えていただき、賞状を受け取りました。
最後は全員が笑顔で終えることができました。
チャレンジマッチに出場した親子と朝飛先生で集合写真も撮影しました。
 集合写真
集合写真
保護者の部
保護者の部には、8名のお父さんにエントリーいただき、団体戦を実施しました。

試合は接戦となり、保護者席や観覧席からの応援もあり、会場は大いに盛り上がりました。
子どもたちが見守る中、保護者の皆さんが真剣勝負を繰り広げ、普段とは違うお父さんの姿に、子どもたちも大きな声で応援していました。
結果は、白組が2勝で優勝。
ケガもなく、無事に試合を終えることができました。
表彰では、出場した親子に賞状とバスクリンをプレゼントし、チームごとに記念撮影を行いました。
 白組
白組 紅組
紅組
表彰式
前半の表彰式では角田夏実先生、髙山莉加先生、後半の表彰式では竹市大祐先生にプレゼンターを務めていただき、メダルや副賞を選手へ手渡していただきました。
2025年度のひのまるキッズ柔道大会は、全7大会を無事に終えることができました。
ご参加いただいた選手・保護者の皆さま、そして大会運営にご協力いただいた関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。
2026年度も引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
明日のブログはブース紹介を予定しております。どうぞお楽しみに!