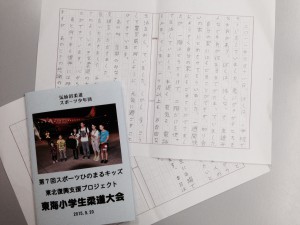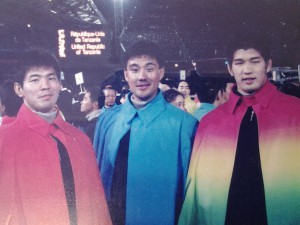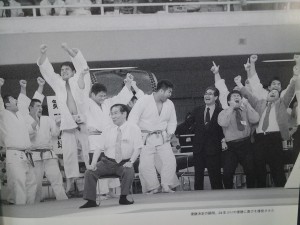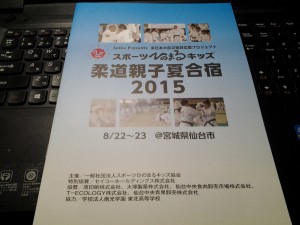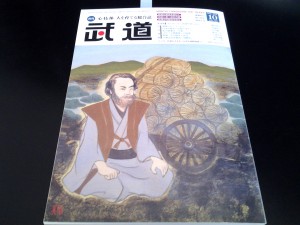2011年3月21日。ぼくは、小学校でそうじをしていました。
急にガタガタと大きなゆれがあり、ぼくは、怖くなって、友達みんなで
ゆれが収まるまでかたまっていました。
自分の家には戻ることができず、知り合いの家にとめてもらいました。
一週間後にようやく家に戻ることができましたが、
一階はどろだらけで、二階だけを使って生活していました。
水道も、電気も、電話も止まってしまい、一ケ月以上も、
不自由な生活をおくっていました。
しかし、今、こうして震災前と同じように、
元気に過ごすことができています。
あの時、全国のみなさんから、たくさんの支援をいただきました。
たくさんの元気と勇気をいただきました。
みなさんのおかげで、このように大きな柔道の大会にも
参加することができています。心から感謝しています。
あと何十年も復興には時間がかかると思いますが、
あの時の感謝の気持ちと、ふつうに生活することが
とても幸せなんだということをいつも忘れることなく、
これからも、勉強に柔道に、そしてぼくたちも大人のみなさんと一緒に
復興にはげんでいきたいと思います。
今日、このような素晴らしい大会に出場できることを
とてもうれしく思います。
本日はどうぞよろしくお願いします。
宮城県 気仙沼柔道スポーツ少年団
選手代表 吉田 陽春
この文は、9月20日に開催した『スポーツひのまるキッズ東海小学生柔道大会』に
ご招待させていただいた気仙沼柔道スポーツ少年団の吉田陽春君が、
大会開会式で、全選手の前で話してくれたものです。
「声が小さくて伝わっていなかったのではないか」と、
指導者の井上剛彦先生が心配され、せっかく書いたものなのでと、
東海大会の思い出をまとめて作られたオリジナルアルバムと一緒に
送ってくださったのでした。
私自身、大会当日は、持ち場を離れることができず、
吉田君の話を聞くことができなかったので、さっそく読ませていただきました。
正直、感動しました。
東日本大震災のとき、吉田君はまだ小学1年生。
親御さんと離れ離れになり、家にも帰れなかった日々は、
計り知れないほど、心細かったと思います。
小さい頃の吉田君のことを知るわけではありませんが、
震災から4年半、つらいこと、悲しいことをたくさん経験したことで、
大きく成長したのだろうと想像します。
「あと何十年も復興には時間がかかると思いますが、
あのときの感謝の気持ちと、ふつうに生活することが
とても幸せなんだということをいつも忘れることなく、
これからも、勉強に柔道に、そしてぼくたちも大人のみなさんと一緒に
復興にはげんでいきたいと思います」
吉田君のこの思いを、東海大会に出場した選手親子だけでなく、
ぜひ多くの人に聞いてほしい、知ってほしいと思い、
紹介させていただきました。
スポーツひのまるキッズ事務局 林